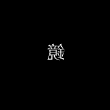
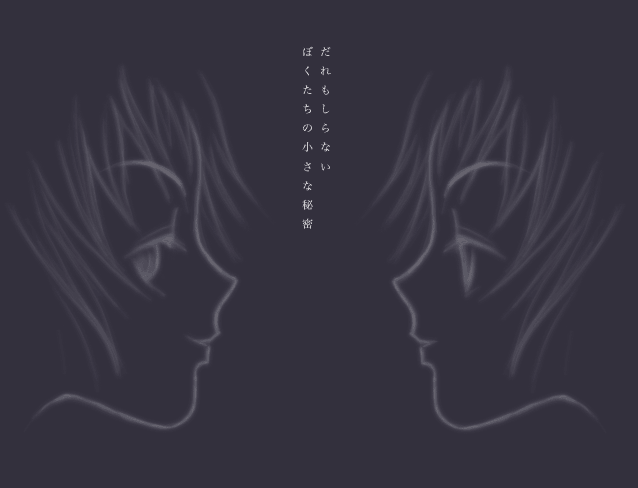
|
「あなた、またここにいるのね。他の子はみんなお昼寝の時間ですよ……セシル君」 セシル、というのはやっと思い出せた僕の名前。セシル君、と呼ばれても違和感なく返事ができるからたぶん、間違いない。 「ごめんなさい」 僕の部屋を出て廊下を右にまっすぐ、突き当たりに皆が食事の後や寝る前などに手を洗ったり歯を磨いたりする場所がある。小さい子のために踏み台がちゃんと用意してあって、僕はいつもそこにのぼって、先生に見つかるまでの短い時間を過ごした。 壁の向こうには、どことなく懐かしい子供の顔がある。僕は友達だと思って会いに来てるのに、いつも不機嫌そうなむっつり顔で僕を見つめてる、ちょっととっつきにくい感じ。だけどなんだか知っている人のような、知らない人のような。 「セシル君だけお昼寝しないのはずるいって、みんなに言われてしまいますよ。さ、お部屋に戻ってくださいね」 「……はい」 素直に返事をして踏み台を降りる。古い木の床の優しい感触が嫌いじゃない。ここは「こじいん」という場所で、僕の家。先生はみんな好きだけど、同じ部屋の子達はうるさいから好きじゃない。おもちゃがどうのとかおやつがどうのとか、泣いたりわめいたり、うっとうしいったらありゃしない。 だから、僕はいつも部屋を抜け出してあの場所に行った。僕と、あの壁の子とふたりで。おしゃべりしなくても文句を言われないのがよかった。だから僕はあの子にだけは僕の秘密を見せてあげるんだ。 静かに目をつむると、やがてふわふわと白いもやが見えてくる。乱暴に掴もうとするとすり抜けてしまうんだけど、何回かに一回かはうまく捕まえられる。そうするとさっきの白いのがぴかぴか光って、僕のいうとおりに飛び回ったりするんだ。でも、あの子はいつも驚きもせずにそれを見てる。 明日はぜったい驚かせてやろう。 「あ、セシルくん、どこいってたの?」 「ずるいぞ!」 「……せんせいに、怒られた?」 「…………別に」 わっと話しかけてきた同室の子供たちに、セシルはそっけなく返事をして机に座った。昼寝の時間なのでみんなあまり大声をださない。騒いでいると先生に怒られるからだ。丁度良いとセシルは喜んだ。 彼が王立孤児院に連れてこられたのはもう数ヶ月も前になる。母親代わりの教師達は皆、友達を作ろうとしないセシルを心配していた。普通、子供は皆同じように遊び、泣き、そしてすぐに仲良くなるものだ。夜となく昼となく、目を離すと鏡の前に立って動こうとしないセシル。教師達もさすがに気味が悪くなってきた頃のことだった。 「せんせいっ! セシルくんがっ!」 深夜、切り裂くような女児の泣き声が廊下に響く。慌てた様子で飛び込んできた年長の子供に付いて教師が洗面所に駆けつけたときには、砕け散った鏡の破片であちこち怪我をしたらしいセシルが呆然と立ちつくしているところだった。 「一体どうしたんです!」 「…………」 血まみれの彼を見て泣きじゃくる子供達の中、セシルは答えない。 「先生、セシル君、魔法を使いました!」 「魔法?」 「ぴかって光ったと思ったら、どかーんって! ね、セシル君」 「…………」 「とにかくみんな、お部屋に戻りなさい。セシル君はまず怪我の手当ですよ、いらっしゃい」 「…………はい」 どうしてこんなことになってしまったんだろう。せっかく、あの白いもやを両手で掴んで出せたのに。あの子が粉々になってしまった。 僕が悪かったのかな。 |