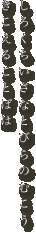
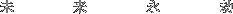
|
光だ。 それは僕の頭のずっと上の方で揺らめいていたようにも、足下のずっと深いところに沈んでいたようにも思えた。手を伸ばしても、もちろん遠すぎてとても届かない。 光のあるところまでゆければ、このまとわりついてくる不快などろどろもきっと無くなるに違いないのにと、ぼんやり残念に思っていたのをよく憶えている。 後になってどれほど苦しかったかと問われても、答えることができたのはそんな曖昧な夢を見ていたことだけだった。あとは、せいぜい喉の奥のひりつく塩水のまずい味くらい。 嵐の夜がどんなに怖かったとか、となりの乗客がどんな悲鳴を上げて海に呑まれていったのだとか、僕の手を握っていた家族が居たのかどうかとか。 そんなことは知らない。憶えていないだけだということすら疑わしいくらいに、すっぽりときれいに記憶は抜け落ちていた。
ただ、あの光だけは、目を閉じれば今もみえる。 |