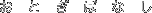
|
翌日、ベイガンの部隊を預かっていたグレニスは別の基地へと去り、セシルはベイガンから本部待機を言い渡された。その日から、仕事ができるわけでもないセシルはただベイガンの隣で、来る日も来る日も彼の仕事を眺めていた。
戦闘は前線を守りつつ一進一退のようで、毎日、大勢の怪我人と死人が運ばれて来た。はじめは本部の窓からそっと覗くだけでも気分が悪くなったが、不思議なもので、半月も経つ頃には平気になっていた。 今回セシルの任務期間はあらかじめ三週間と決められている。セシルには出撃の命令は出ない。ベイガンはこのまま自分を一度も戦場に出すつもりはないのだろうかと思いはじめた、ある午後のことである。 「大佐っ! 第1〜5小隊、壊滅の模様です!」 「北方に敵の新手が! 援軍です!」 「…………」
伝令兵の悲痛な声に司令部の面々は思わず黙り込む。 「第8、第9小隊、いずれも壊滅!」 「……なんてことだ!」
ベイガンが両手で机を叩く。 「…………」 「大佐っ! ご指示を!」 「ベイガンさん?」 「……動ける者は撤退の準備を! この基地は放棄する!」 「はっ!」 「…………?」
意外な言葉にセシルは目をみはる。 ここには怪我人も大勢いるのに。 迫り来る地鳴りのような音は、数え切れない馬の蹄の音。平原の速駆けに慣れたこの国の騎兵は速くて強い。セシルは、追われる身として初めての戦場に立つことになった。 砂埃が目に痛い。沈みゆく夕日が見える時刻であるはずなのに、あたりは生明るいだけで太陽がない。 殿軍の必死の防戦を後目に、海岸線をひた走る。しかし、日暮れには再びの窮地が逃げ落ちる部隊を襲った。 「……ふん、つまりはじめから袋の鼠だったということか」 前方を取り囲む敵兵の影に、ベイガンは忌々しげに言った。 「戦闘はまぬがれません」 「そのようだな……」 ベイガンの言葉が終わらぬうちに、辺りの殺気が唐突に剣呑なものに変わり、息つく暇もなくわっと兵達が動き始める。 「数は多くない! 突破だ!」
これは、いったい。 「セシル殿は私の傍を離れるな!」
目の前には、はじめて見る知らない制服の敵兵。
今は 「…………ぁあああああっ!」 「セシル殿!」 こちらへ向かってくる数人の敵兵が、なぜかコマ送りのようにのろのろと動いて見える。ベイガンはどこだろう。声が遠い。ああ、離れてしまったのか。
あの暖かな中庭の日差し、海から来る気持ちの良い午後の風。 けれど海の向こうは遠くて、あまりにも遠くて。 「ローザ……」 目に入る血塗れの剣。そうか、次は僕か。 「…………陛下……」 セシルは目を閉じ、そして永遠にも似た闇の底へと沈んでいった。 |