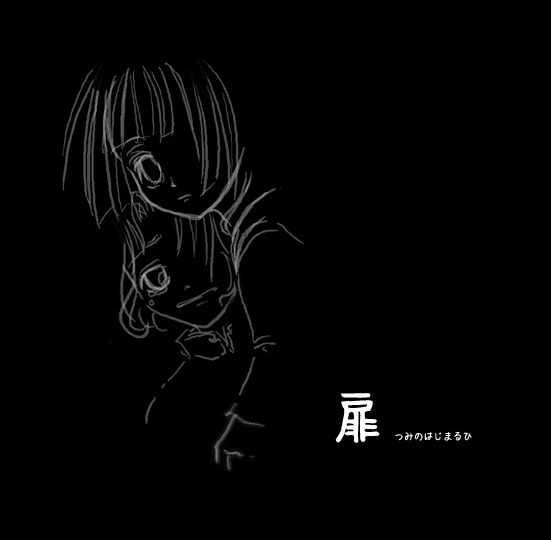
|
秋の一大イベントといえば収穫祭を置いて他にない。今年もそんな祭りの準備に忙しい季節がやって来ていた。忙しく走り回る大人達を後目に退屈顔のセシルとデュアルは、ぼんやりと高い秋空を眺めていた。 「父上たち、当分あんな調子でお忙しいのだろうな」 「ですね」 「あーあ、勉強の時間がないのは良いが、庭で遊べないのはやだよな」 「仕方ありませんよ、収穫祭は王子もお好きでしょ?」 そう言って窓の外に目を移した刹那、パンという軽い音が響いた。何となしに音のした方を見やる。祭りで使う花火を誰かが戯れに打ち上げたのだろうかと思っていると、あと数回、同じ乾いた音。変だな。城門辺りがにわかに騒がしくなりはじめた。近衛兵達が慌てた足取りで門の方へと走っていく。嫌な予感。なんだろう……あれは、そう。 銃声。 「王子!」 「なんだ? 何かあるのか?」 王子はきょとんとした顔でこちらを見ている。異変に気づいていないらしい。どうしよう、恐ろしい。王子を連れて逃げなければ。でも、縫いつけられたように足が重い。もう一度窓の外に目をやる。黒い勤務服の人間が何人か倒れているのが見えた。外は白々しいほどの秋晴れ、ああ、なんてこと。 「どうした? セシル? あれは何だ?」 「王子……」 デュアルの顔がみるみる青ざめていく。何か言って励まさなくちゃ、この方泣き出すと動けなくなるから。だけど、さっきから鳴りやまなくなったあの炸裂音と薄い硝煙が、僕の喉を震えさせて、うまく声が出ない。 「王子っ! セシル君も!」 立ちすくむ二人の所へ息せき切らして走り寄ったのは、勤務中であった様子のクライヴだった。いつもいい加減で軽薄そうな笑みを浮かべているクライヴが血相を変えて、抜き身の剣なんて手にしている。 「なにか、あったんですか?」 なるだけ平静を装って口にした言葉は、妙に低く呟いたように滑稽にきこえた。クライヴはそんなセシルの様子に気がついたのか、ふと表情を緩めると、剣を収めた。怒号が飛び交う外をちらりと見て、それからしゃがんで二人に目を合わす。 「いや、大丈夫。ちょっとね」 「クライヴさん……」 「こ、近衛兵! ぼくは……」 「王子、大丈夫。大丈夫ですよ。陛下の所へ行きましょう」 ローザと同じ琥珀色の目がとても優しい形で彼を見たので、床に彼の足をきつく縫いつけていた糸が切れていく。大丈夫、大丈夫。 だいじょうぶ、走れる。 「陛下!」 「ちちうえ!」 灯りの落ちた薄暗い廊下で数人の護衛のみの王が二人を抱きしめた。 「二人とも、無事であったか」 「父上、一体なにが?」 「ああ……大丈夫だ、心配しなくていい」 「?」 王はいつもと同じように優しかったが、その顔は随分疲れているようにみえた。余裕そうに笑ってみせたクライヴの横顔にもくっきりと焦りの表情が浮かんでいる。どうしたんだろう。何があったんだろう。 「さ、ゆくぞ二人とも」 「父上?」 「セシル君も」 「…………」 連れて行かれたのは、カーテンの引かれた暗い書庫。その膨大な本棚の中にひとつだけ、地下へと続く入り口を隠しているものがある。隠し通路、セシルもデュアルも今日まで知らなかった。 階段はいやに長く感じられ、このまま地獄の底まで降りていってしまうように思えたが、やがて平坦な通路に出て、そこにはいくつかの部屋があった。錆びた重そうな扉は、子供の手では開きそうにない。 「ふたりとも、しばらくここに隠れていなさい」 「な、何をおっしゃるんですか、父上!」 「陛下……陛下は?」 「私は大丈夫だ、終わったらすぐに迎えにくる」 「嫌です父上!」 「陛下、急ぎませんと」 「デュアル、セシル……大切な子供たち……」 クライヴが手にしたランプが、前に立つ王をぼんやりと光で縁取る。顔の見えない王が微笑んでいることは気配でわかる。静かに、王は言った。 「必ず戻る……待っていてくれ」
後には、立ちはだかるかのように閉ざされた鉄の扉。 |